|
|
 |
|
 |
|
|
ホメオパシーとは |
|
|
|
|
  ホメオパシーの語源 ホメオパシーの語源

ホメオパシーとは、ギリシャ語のhomoios (似たような)とpathos(苦しみ)のふたつの言葉
を合わせた造語で、日本では「類似療法」または「同種療法」と訳されています。
これは、ホメオパシーの原理の一つに由来したものです。

 ホメオパシーの起源 ホメオパシーの起源

風邪をひいてノドがヒリヒリと焼けるように痛く、熱で体中が熱くなっているときに、すりおろした生姜に熱いお湯を注いだ生姜湯を飲んだ経験をお持ちの方も
いると思います。昔はこれが風邪の特効薬でした。ところが健康な時にこの生姜湯を飲むとどうでしょう。ノドは焼けるようにヒリヒリと痛み、体がポッポと熱
くなって行くことでしょう。これが「似たものが似たものを治す」というホメオパシーの基本的な考え方です。

このような方法は、インドのチャラカCharaka(紀元前1000年頃)、ギリシャの医学の祖と呼ばれたヒポクラテスHippocrates(紀元前
400年頃)、
中世ヨーロッパでは、医師であり錬金術師でもあったパラケルススなどの医療者たちも行っていたことが書き残されており、世界の各地で実践されていた様子が
伺えます。そしてそれをホメオパシーとして体系化したのが18世紀のドイツの医師ハーネマンでした。

ハーネマンは瀉血が治療の中心であった当時の医療に幻滅して医師を辞めますが、ある医学書を翻訳している時に、当時マラリアの特効薬と言われたキナ(ペル
リアン
バーク)という植物の樹皮の説明に、「キナの皮は苦みがあるためにマラリアの治療に効く」という記述を見つけ、それに疑問を持ちます。なぜなら苦みを持つ
植物なら他にもたくさんあるからです。そこでハーネマンは自らこれを飲んで実験を試みました。すると驚くことにマラリアとそっくりな症状が現れました。動
悸、脱力、疲労、倦怠感、不安感、交互に現れる熱感と悪寒、大量の汗、口渇など。そしてその飲用を止めるとそれらの症状は全て治まるのです。このことが大
きなヒントとなり、「ある症状を起こすことのできる物質はその症状を治すことができる」という類似の法則を発見します。

ハーネマンは様々な物質を用いて同様の実験を行い、健康な人にどのような変化が起こるのかをつぶさに観察し、詳細な記録を取り続けました。また、それに
よって実際に病人が治ることを確認しながら、ホメオパシーを確立していきました。

 ホメオパシーの原理 ホメオパシーの原理

「似たものが似たものを治す」という原理の他に、ホメオパシーの考え方の中で、もう一つの柱となるのが「Vital
Force」の考えです。日本語にすると、「生命力」「自然治癒力」に該当するかもしれません。ホメオパシーのレメディはそこに働きかけるのです。それに
よって心も体も同時に乱れたバランスを取り戻して行きます。

「似たものが似たものを治す」と「Vital
Force」の二本の柱が、ホメオパシーの哲学を支えています。そして何よりも、ホメオパシーの基本かつ重要な哲学は、「病気を癒すのではなく、病気を
持った人を癒す」というその人全体(精神、心、体)の真の治癒を目指して行くことにあります。
 
 歴史 歴史

19世紀初頭は、ヨーロッパ各地でコレラや猩紅熱、黄熱病、チフスといった感染症が流行した時代ですが、これらの病気に対するホメオパシーの効果はすばら
しいものでした。ハンガリーのラーグでは、従来の治療を受けたコレラ患者の約59%が亡くなったのに対し、ホメオパシーによって治療された患者で亡くなっ
たのは154人の内わずか6人だけでした。こうした臨床的な成功から、ホメオパシーはヨーロッパ全土だけでなくアメリカにまで急速に広がりました。アメリ
カでは19世紀後半の全盛期に、56のホメオパシー病院、13のホメオパシー治療を行う精神病院、9のホメオパシー小児病院、15のサナトリウムがあり、
専門教育を受けたホメオパスが何千人もいたと言われています。

しかし20世紀に入り、抗生物質の発明や細菌の発見などにより現代医学が優勢になり、ホメオパシーは一時期衰退します。しかし、1970年代頃から再び注
目を集めるようになりました。その理由として、新しい耐性菌の台頭や慢性病の増加、現代医学の薬の副作用への恐れなどから人々が現代医学に疑問を感じると
ともに、心と体を同時に治癒するホメオパシーに惹かれるようになってきたからだと考えられます。
 
 世界の現状 世界の現状

今日ホメオパシーは、ヨーロッパ諸国、アメリカ、南米諸国、インド、オーストラリア、ニュージーランドなどで盛んです。英国では国内の5カ所にホメオパ
シー病院があり、ホメオパシー治療は国民健康保険の対象になっています。王室がホメオパシーを取り入れ、国民にも熱心に推奨しているのは有名です。アメリ
カでは1970年代に西海岸を中心にホメオパシーの人気が高まりましたが、今はそれがNY、ボストンなどの東海岸の大都市に移って再度隆盛期を迎えている
と言われています。ちなみに「統計によると1990年にはホメオパシーレメディの利用者が全米で250万人を超え、ホメオパシー受診者は80万人を超えて
いる」とあります。フランスでは市販される薬の30%はホメオパシーレメディであり、国民の3分の1がホメオパシー治療の経験者です。ドイツでもホメオパ
シーは
非常に人気があり、英国、フランス同様、国民健康保険の対象です。南米のホメオパシーも水準が高く、何千人ものホメオパスがいます。インドでは、ホメオパ
シーは政府に認可されており、十分に援助が行われています。世界で最も多くのホメオパシー病院がある国で、ホメオパスも30万人以上います。4年制または
6年制のホメオパシー医学校が40あり、ホメオパシー関連の本も多く出版されています。オーストラリア、ニュージーランドでもホメオパシーは急速に発展し
つつあり、医師と専門家のホメオパスの両方が治療を行っています。21世紀の代替療法のホープと言われているホメオパシーは、今後より多くの人に求められ
る療法となるでしょう。
 |
|
|
| レメディとは |
|
|
|
|
 定義 定義

ホメオパシーで使用されるものをレメディと呼びます。
レメディは植物、動物、鉱物などから作られ、3,000〜4,000種類あると言われています。

 レメディの作り方 レメディの作り方

レメディは、原物質を蒸留水とアルコールを混ぜた溶液で薄めて(希釈)、それを振ること(振とう)を繰り返しながら作られます。実際には、その薄めた液を
染み込ませた乳糖の丸薬や錠剤を摂ることになります。

 ポーテンタイゼーション ポーテンタイゼーション

原物質の分子が無くなるほど極限まで薄め、さらにそれを激しく振ってレメディを作ることをポーテンタイゼーションと呼び、ホメオパシーの大きな特徴の一つ
です。その薄め方の度合いはポーテンシーという言葉で表されます。
 
 30Cはどれくらい薄いか? 30Cはどれくらい薄いか?

薄める方法には10倍希釈法と100倍希釈法があり、10倍希釈法はX(ドイツではD)で、100倍希釈法はCで表されます。たとえば欧米の薬局などで手
軽に買える30Cというポーテンシーは、抽出物の原液を100倍に薄め、それをさらに100倍に薄めるという工程を30回繰り返したもので、10の60乗
分の1という薄さになります。これはわずか1ccを一辺が1,000兆キロメートルの立方体に垂らしたのと同じ薄さです。
 
 セルフケアには30C セルフケアには30C

一般的に希釈度が高いものほど、すなわちポーテンシーが高いほど、体よりも心により作用すると言われていますが、個人差があり一概には言えません。
セルフケアではよく30Cが使われます。 |
|
|
|
 |
|
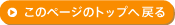  |
|